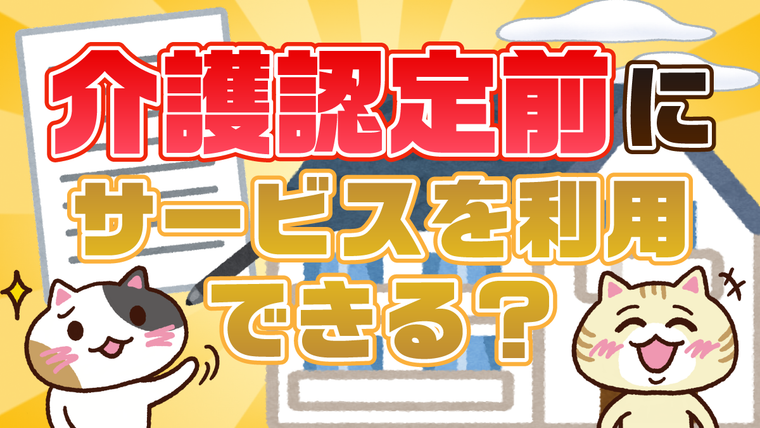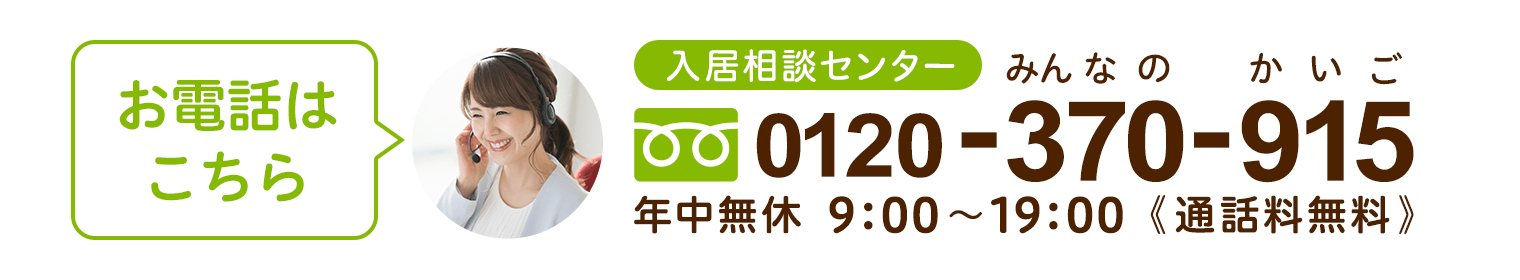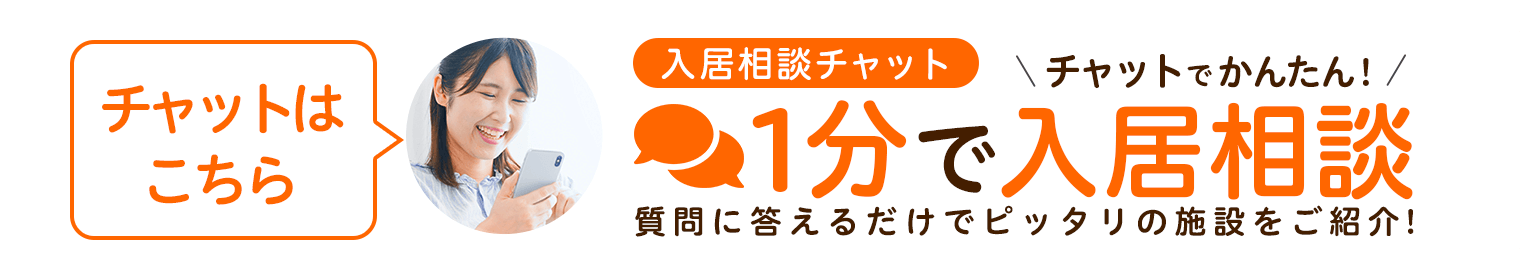介護保険サービスは要介護認定の申請日から利用可能
通常は、結果通知書を受け取り、介護度の段階を確認後、介護サービスの利用を始めるわけですが、本人の心身状態あるいは住環境によっては、結果を受け取るまで待てないケースもあり得るでしょう。
例えば、「近日中に退院する予定だが、自宅に戻ってからすぐに訪問介護を利用したい」「転倒の恐れがあるので、急いで介護リフォーム(住宅改修)を行いたい」といった場合です。
そこで、介護保険制度では、結果が通知される前であっても「後日、要介護認定が下りたときに、申請した日に遡って保険給付を受ける」という形でサービスを受けることができようになっています。
認定結果が非該当(自立)の場合は全額自己負担になるので要注意
申請日を開始日として介護保険サービスを利用することはできますが、ここで注意点が2つあります。
ひとつ目が、要支援、もしくは要介護の認定を受けられなかった場合は、利用したサービスの料金が全額自己負担になってしまうということ。ふたつ目は、それぞれの介護度には支給限度額が設定されており、仮に想定していた介護度よりも低い認定を受けた場合、想定していたよりも高い金額を支払わなければならないことです。
以上の2点に注意して、どのサービスをどの程度利用するのか決めましょう。
また、在宅介護サービスを利用する場合の要支援、要介護度に応じた支給限度額の表を作成してあるので参考にしてください。
| 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |
| 要支援2 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |
| 要介護1 | 1万6,355円 | 3万2,710円 | 4万9,065円 |
| 要介護2 | 1万8,362円 | 3万6,724円 | 5万5,086円 |
| 要介護3 | 2万490円 | 4万980円 | 6万1,470円 |
| 要介護4 | 2万2,435円 | 4万4,870円 | 6万7,305円 |
| 要介護5 | 2万4,533円 | 4万9,066円 | 7万3,599円 |
※1単位―10円の場合
※上記額面は30日換算で算出した金額
納得できる認定結果が得られなかった場合は?

「想像していた介護度よりも軽く判定された…」と、要介護認定に納得がいかない場合にとれる方法を2つご紹介します。
まずひとつ目は、都道府県の介護保険審査会に対して、要介護認定を取り消してもらうための申し立てを行うことです。
ただ、取り消し判定が出るまで数ヵ月かかり、取り消されたとしても、また最初から介護申請をしなければなりません。
そこで、ふたつ目のおすすめは、市町村自治体に対して要介護認定の区分変更申請を行うことです。
認定結果が出てから60日以内に申請が必要な介護保険審査会への申し立てとは違い、区分変更申請はいつでも行うことができます。
認定前に老人ホームを探すときの注意点
要介護認定を申請していれば、介護保険被保険者証(保険証)がまだ手元になくても、老人ホームに入居できます。
入居条件が要介護以上3の方に限定されている特養の場合は入居できませんが、申し込み自体は可能です。
どうしても特養に入居したいという方は、以下のようなケースに該当している必要があります。
- 認知症があり、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られること
- 家族などによる深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
- 単身世帯であったり、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域の介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
見学の段階で「まだ認定が下りていない」ことを伝える

老人ホームの見学の段階で、介護保険証がまだ届いていない場合は、担当者にそのことを事前に伝えてください。
契約時または入居前に提出すると、施設側から「待った」がかかる場合も考えられます。
介護保険サービスを利用するには、さまざまな職種の連携があって初めて成り立つもの。常になるべく早めの報・連・相を心がけましょう。
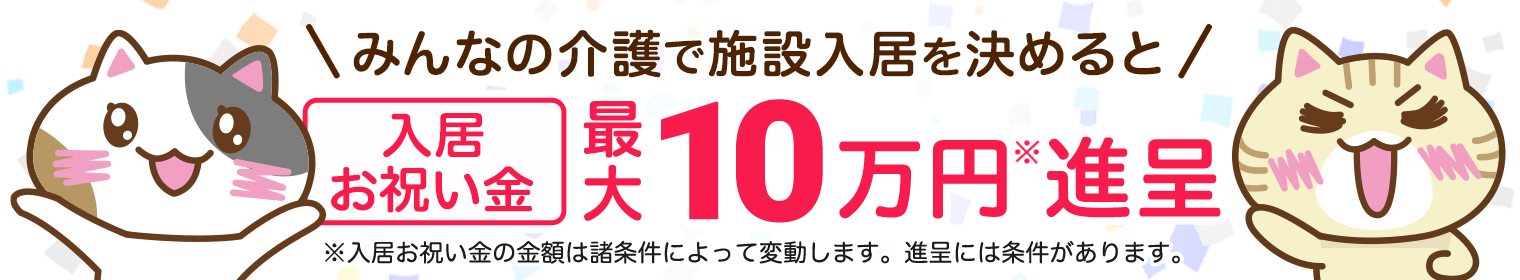
要介護認定の結果が出るまでの目安は30日

要介護認定の申請から認定までの一連の流れは、以下の通りです。
- 1.申請
- 申請書や介護保険被保険者証などの必要な書類を提出し、受理された後、提出した介護保険被保険者証に代わるものとして「介護保険資格者証」の交付を受ける。
- 2.日程調整
- 書類の提出後、市区町村側から訪問調査の日程調整をお願いする連絡が来たときに、調査員が自宅に訪問(入院中の場合は病室への訪問)しても良い日時を伝える。
- 3.一次判定
- 市区町村の担当者もしくは委託されているケアマネージャーが申請者のもとを訪問して聞き取り調査を実施し、さらに市区町村から申請者の主治医に対して、意見書を作成するよう依頼が行われる。
- 4.二次判定
- 一次判定の結果と主治医の意見書、さらに提出された各種必要書類から、介護認定審査会が要介護認定の判定を行う。
- 5.結果の通知
- 申請後30日以内に、認定結果および介護保険被保険者証が申請者に郵送される。結果内容は、要支援1~2、要介護1~5の7段階のいずれか、もしくは介護サービス利用対象外である「非該当」(自立)。
認定前に利用できる介護保険サービスの利用方法
介護サービスは、ケアマネジャーが利用者の介護度や生活状況に応じて、介護サービスの利用計画書である「ケアプラン」を作成することではじめて利用できます。
要介護認定の結果通知前に介護サービスを利用する場合でも、ケアプランが必要であることに変わりありません。
どうするかというと、「暫定ケアプラン」なるものを作ってもらうのです。
しかし、認定が下りる前だと、あくまでも想定される介護度に応じたサービスを組むしか方法はありません。
そのため、後日通知された介護度が想定していた介護度より低い場合、利用した介護サービス費の合計が支給限度額を超えると、超過分については全額自己負担での支払いを求められます。
認定結果が通知される前に介護サービスを受けたいときは、地域包括支援センターあるいはケアマネジャーとよく相談しておくことが大切です。
認定前におすすめの介護保険サービス
要介護認定の結果を待つ間、健康状態が比較的良好な方であれば、まずは市区町村や民間企業などが実施する介護予防サービスの利用をおすすめします。
介護予防サービスには大きく分けて2つあります。
認定結果を待っている方は、想定している要介護度よりも軽い認定をされても自己負担が増えるリスクがないので、②の利用がおすすめです。
- 介護保険:要介護(要支援)認定を受けている方のための介護予防サービス
- 市区町村:65歳以上の誰もが利用できる介護予防サービス
介護予防サービスは、自己負担0円~1回当たり数百円程度で利用できるものが多く、経済的な負担を気にせず参加できるのが大きな魅力です。
提供されている具体的なサービスは自治体ごとに異なりますが、「体操教室」や「脳トレ」、各種健康関連の相談会や専門家による講話などが多いようです。
介護リフォーム(住宅改修)は工事が終わるまで時間を要するので早めに

65歳以上の日常生活動作に不安がある人を対象者に、自立支援のために住宅改修について、独自の給付制度を設けている市町村は少なくありません。
必要性が認められると、市区町村から介護リフォーム費用(住宅改修費)の一部が支給されます。
ただし、工事の前に、工事費補助の申請が必要です。
リフォーム後の事後申請は認められず、全額実費負担となってしまうのでご注意ください。