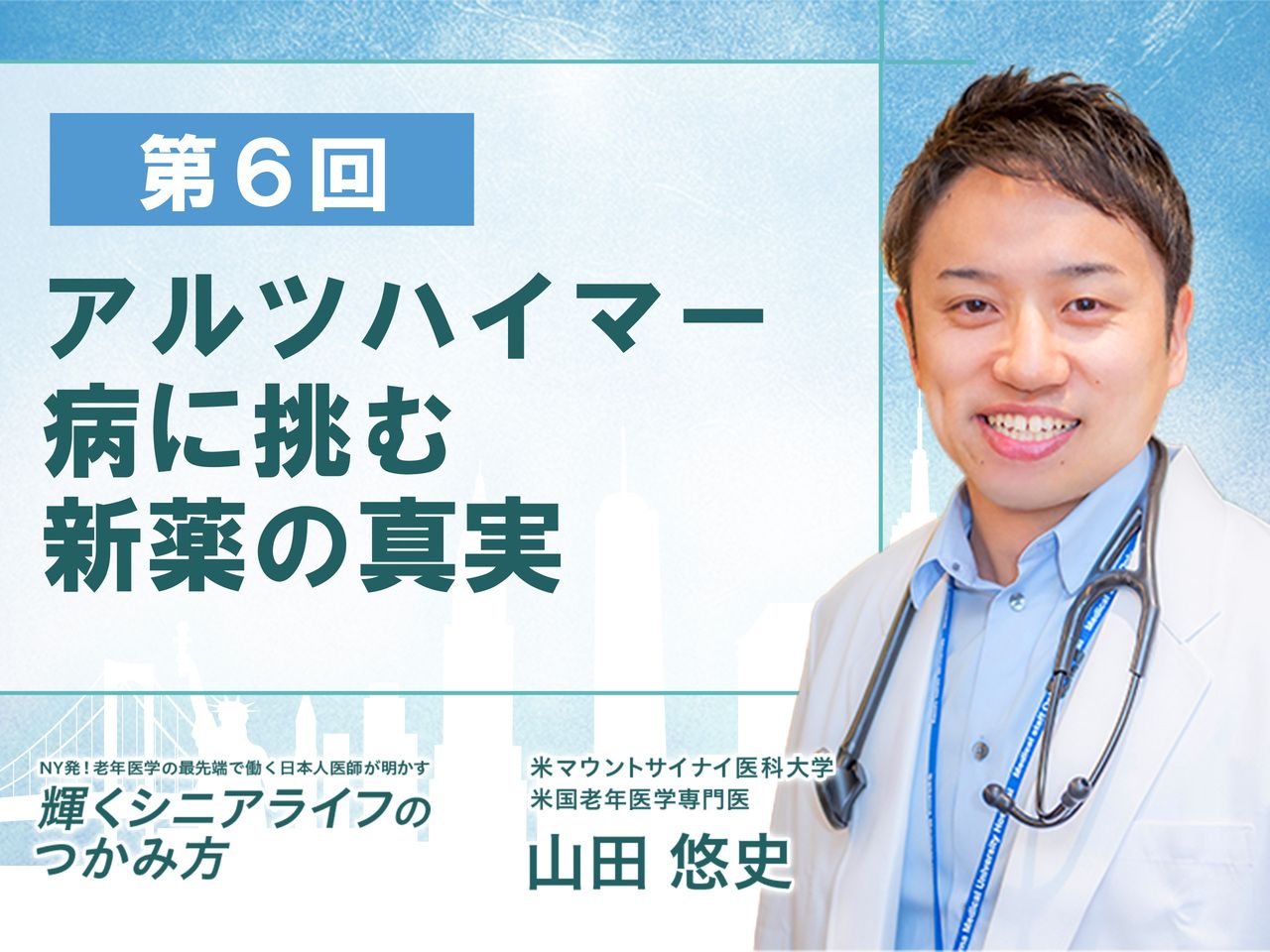記憶は、私たちのアイデンティティの核であり、大切な人々とのつながりを形作る絆でもあります。しかし、アルツハイマー病はその記憶を脅かし、私たちが最も大切にしているものを奪うかもしれない病です。長年にわたり、この病との闘いは遅々として進まないものでした。しかし今、新たな治療薬が、この闘いに変化をもたらそうとしています。
何十年にもわたる研究努力と失敗の末、新たな治療薬はアルツハイマー病の根源の一つと信じられるところにアプローチし、患者さんとその家族に新たな希望を提供するかもしれないとの期待を寄せられています。しかし、これは決して単純なサクセスストーリーではありません。効果の大きさ、副作用、治療コストといった現実が複雑に絡み合っています。この記事では、この度登場した新薬がアルツハイマー病治療においてどのような道を開くのか、その効果と副作用、そして未来への展望を解き明かしていきます。
新薬レカネマブ
アルツハイマー病の治療薬として新たに登場した薬。それがレカネマブです。この薬はアルツハイマー病の原因の一端を担っているのではないかと考えられているアミロイドβに対する抗体薬です。このアミロイドβというのは、「脳に溜まるゴミ」と形容されることもあります。これを取り除くことによって、ゴミのなくなった綺麗な脳は再び認知機能を回復するのではないかと考えられたのです。
レカネマブは、2週間に1回、静脈内に注射して投与をする「抗体薬」です。薬といえば、飲み薬をイメージする方も多いかもしれませんが、一般的に抗体を用いた薬剤は注射が必要になります。
なお、「抗体」というのは、パンデミックでご存知の方も多いかもしれませんが、本来体の中でウイルスなどの外敵を攻撃し、取り除くためのものです。
そして、この抗体を病気の原因に働きかけるようにデザインして作ったものが抗体薬です。この薬を投与することで、脳に蓄積した「ゴミ」であるアミロイドβを取り除くことができ、それによりアルツハイマー病をよくできるかもしれないと期待を持たれてきました。>
レカネマブ開発までの道のり
しかし、実際にはこのレカネマブに辿り着くまでに類似薬が何度も失敗を重ねてきました。もはや、アミロイドβをターゲットにするのはやめた方がいいのではないかという議論が出ていたほどです。しかし、そこにほんの僅かの光明を差した出来事がありました。2021年のアデュカヌマブの誕生です。
アデュカヌマブも、アミロイドβを狙い撃ちする抗体薬であり、画像検査でアミロイドの減少を示しました。2021年6月、アメリカ食品医薬品局(FDA)は主にこの画像検査の結果に基づいて、史上初のアルツハイマー病治療薬としてアデュカヌマブに迅速承認を与えたのです。しかし、これは議論の余地がある決定でした。なぜなら、早期終了された2つの臨床試験で、効果に矛盾する証拠があったからです。
しかし、今回のレカネマブは、その矛盾を乗り越えたのです。
矛盾を乗り越えたレカネマブの実力
レカネマブの承認にあたっては、18ヶ月に渡り有効性を評価する第三相試験が行われています。この試験のポイントの一つは、過去の類似薬の試験で、より進行したアルツハイマー型認知症の患者を対象としたのとは対照的に、比較的初期の、軽症のアルツハイマー病患者のみを集めたという点です。より進行した段階で薬剤の投与をしても「時すでに遅し」で、早期の段階で投与してこそ効果が発揮できると考えられたからです。
結果をみてみると、これは副次的な評価項目ですが、肝心のアミロイドβはアデュカヌマブと同様、確かに著しく減少していることが確認できました。そうなると、認知機能回復にも大いに期待が持たれます。
しかし、蓋を開けてみると、期待されたような認知機能の回復は見られず、残念ながらレカネマブを投与した人たちでも認知症の症状に確実な進行が見られていました。とはいっても、偽薬の投与を受けた人と比較すれば、レカネマブを投与された人で、その進行が遅くなっていました。
その差がどのぐらいだったかと言えば、18点満点のスケールで0.45点の差、進行の度合いで言えば、進行を27%遅くしたという結果でした。これがこの薬の「有効性」ということになります。数字について、比較的大きいという感覚を抱かれるかもしれませんが、差分を見れば、残念ながら意味のある差ではない可能性が高いと言わざるをえないでしょう。
また、もう一つ重要なのは、あくまで認知機能を改善する効果は見られず、「進行を遅くする」効果にとどまったという点です。このため、おそらく投与を受けている患者さんには、薬の効果はほとんど実感できない可能性が高いと考えられます。もちろん、認知症の患者さんや家族は、「目にみえる効果」を期待して投与を受けるでしょうから、そこには大きなギャップが生まれるかもしれません。
ただそうはいっても、同種薬剤で初めて、事前に決められた主要なアウトカムで有意な差が見られたということ自体は歴史的な快挙であったとも思います。

懸念されるレカネマブの安全性
「効果が実感できるようなものではない」という点に加えて、安全性への懸念もあります。一定の割合で脳浮腫や脳出血が生じる可能性が報告されているのです。薬を投与された人の12.5%に脳浮腫、17%に脳内の出血の副作用が見られています。ただし、試験で観察された範囲内では、例えば脳浮腫では91%と、大部分が軽症から中等症であったと報告しています。
どのような人で脳出血などの副作用が多いかをみてみると、ApoE ε4と呼ばれる遺伝子変異を持つ人(アルツハイマー病との強い関連性が知られている)で多いこと、また、これは当然と言えば当然ですが血をサラサラにする薬を飲んでいる人でそのリスクが高い可能性が指摘されています。
脳梗塞治療中に死亡した例も報告されており、そうした治療薬の併用には警告が行われています。アルツハイマー病を抱えた方には、血をサラサラにする薬を飲まれている人が多いため、投与する患者さんの選択には十分慎重を期す必要があるでしょう。
また、一般に抗体薬は薬価が高額となります。抗体薬投与前後には高額な検査も必要となります。効果が限定的であることをふまえると、費用対効果が見合わない可能性もあり、保険料を支払う国民のコンセンサスを得られるものなのかという意見も聞かれて然るべきだと思います。
レカネマブの「次」
実は同種の薬剤で、もう一種類、承認を控えている薬剤もあります。その数字の大きさから、こちらが本命ではないかという噂すらあります。それがドナネマブです。レカネマブの場合と同様に、ドナネマブは脳からアミロイドを取り除く印象的な「効果」を示しました3。
臨床的には、臨床認知症評価尺度(CDR-SB)の合計点数を見ると、ドナネマブを受けた患者さんの認知症の重症度は18ヶ月で1.72ポイント悪化したのに対し、プラセボを受けた患者さんは2.42ポイント悪化し、18点満点の尺度で0.7ポイントの差がありました。割合で見れば、「35%抑制した」という表現になり、一見レカネマブよりも印象的な数字に見えます。しかし、差の数字で見るとやはりその効果は限定的と言わざるをえません。
しかし、吉報もあるかもしれません。ドナネマブを受けていた患者の中で「タウ蛋白」と呼ばれるアミロイドβとはまた別のタンパク質の沈着が比較的少ない参加者では、47%が投与開始後1年の時点で認知機能が大きく変化していないと考えられました。これに対してプラセボを受けた参加者では29%でした。これは、タウ蛋白の少ない一部の人々にとっては臨床的に意味のある差を生むかもしれないことを示唆しています。
一方で、懸念するような報告もあります。まずは、先述と同様の脳浮腫、脳出血の副作用が報告されているという点を挙げておかなくてはなりません。治療薬に関連すると判断された死亡は3名にも上ります。また、確かにアミロイドはきれいに取り除かれていて、MRIの写真を見ると、ドナネマブの投与を受けていた患者の方が記憶を司る脳の「海馬」という領域も維持されていたものの、驚くことに脳全体の萎縮はむしろ進行する傾向にありました。
これは、他の同種薬剤でも繰り返し報告されている事象であり、観察期間である18ヶ月を経た後に、こうした変化が認知機能の悪化を示唆するものであったと判明しても不思議ではありません。試験期間は18ヶ月。それを超える時期の長期の有効性、安全性はまだわかっていません。
アルツハイマー病治療の新たな地平
アルツハイマー病の世界は、治療の進歩が大きく滞っていた中で、こうした薬の開発が歴史的な一歩となったことは間違いないでしょう。少し未来の話をすれば、アミロイドβ治療薬が、将来の個別化医療の1ピースを担うことになっていても全く不思議ではありません。
しかし同時に、これまでの臨床試験の結果は、アルツハイマー病の複雑さを浮き彫りにしたとも言えます。ドナネマブやレカネマブがアミロイドを除去する能力は高いにも関わらず、認知機能や日常生活の機能の衰えの速度に対する効果は限定的であることは、少なくともアミロイドβがアルツハイマー病の進行に寄与する唯一の要因ではない可能性が高いことを示唆しています
より実用的な視点では、もし抗体薬のリスクがほとんどなく、安価で、簡便に投与できるものであれば、患者も医師も、この限定的な利益で議論を起こすことはなかったと思います。しかし、現実はその真逆。ドナネマブとレカネマブの研究では治療関連の死亡がそれぞれ3件ずつ報告されているのです。また、繰り返しになりますが、大きなコストも課題です。薬自体のみならず、遺伝子検査、副作用確認のためのMRI検査、治療を中止するタイミングを決めるための追加のPET検査など、治療に関連する多くの追加コストもかかります。
こうした薬の持つリスクが限定的なメリットとの間でバランスが取れるかどうかを判断するには、より多くのデータが必要なのは明白です。治療薬を受けたグループとプラセボを受けたグループの違いが、18ヶ月を超えても増加し続けるのかどうか、認知機能や日常生活の機能、生活の質、そして介護者の負担への効果をより長期に見ていく必要があると思います。さらに、治療薬を受けた人で見られている脳の萎縮が後々の経過の中で否定的な影響を与えないのか、まだ予期されていない追加リスクがないかどうかを確認することも重要です。
日本人という視点では、先の試験でアジア人がほとんど含まれていないことから、日本人のデータを蓄積していくこともまた、重要になるでしょう。
ここまでの研究では、アルツハイマー病を早い段階で治療するために特定のタンパク質を攻撃する薬がどれだけ効くかが調べられています。しかし、それでこの病気の解決につながるとは思えません。将来は、アルツハイマー病になるプロセスに関わる他の要因も狙い撃ちするような新しい薬を組み合わせて使う必要があるかもしれません。
そうは言っても、少しずつですが、アルツハイマー病に立ち向かうための研究は確実に進歩してきていて、新しいタイプの治療法が次々と登場してきています。これらの新薬が、いずれアルツハイマー病を治療する新たな地平となる日が来るかもしれません。
参考文献
1. Rabinovici GD, La Joie R. Amyloid-Targeting Monoclonal Antibodies for Alzheimer Disease. JAMA. 2023;330(6):507-509. doi:10.1001/JAMA.2023.11703 2. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease. N Engl J Med. Published online November 29, 202 doi:10.1056/NEJMOA2212948/SUPPL_FILE/NEJMOA2212948_DATA-SHARING.PDF 2. 3. Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330(6):512-527. doi:10.1001/JAMA.2023.13239 4. Widera EW, Brangman SA, Chin NA. Ushering in a New Era of Alzheimer Disease Therapy. JAMA. 2023;330(6):503-504. doi:10.1001/JAMA.2023.11701