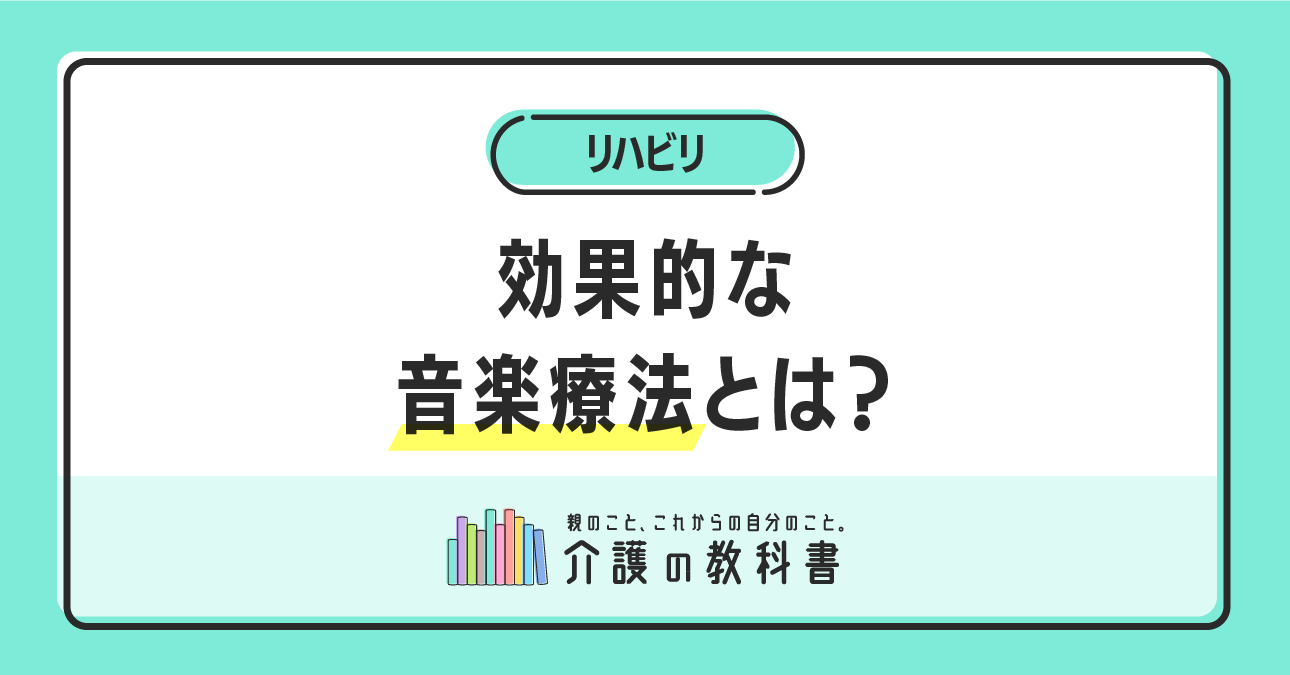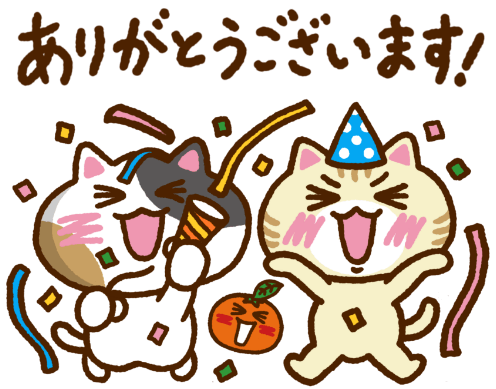皆さんは音楽療法と聞くと、どんなイメージを持ちますか?
現在高齢者にも広がりを見せているノードフ・ロビンズ音楽療法について、ノードフ・ロビンズ音楽療法士である長江朱夏先生にインタビュー。
そして長江先生おすすめの音楽を通したコミュニケーション術について伺ってきました。
身近な音楽を真似るだけでも取り組めますので、ぜひご活用ください!
ノードフ・ロビンズ音楽療法の特長
今井:音楽療法という言葉を、最近耳にする機会も増えてきました。しかし、ノードフ・ロビンズ音楽療法というのはあまり馴染みがありません。どのようなものなのでしょうか?
長江先生:1950年代初頭に作曲家であるノードフと、教育家のロビンズによって創り出された、音楽療法のアプローチ方法のことを指します。
世界的にも有名なアプローチ方法の1つで、障がい児(ダウン症や自閉スペクトラム症、発達障がいのある子ども)との取り組みに、即興音楽を用いたことが始まりでした。
このような子どもたちは、感情を共有することや対人関係を築くのが難しいなど、コミュニケーション能力がうまく引き出せていない状態です。
そこで、ノードフ・ロビンズ音楽療法の特徴の1つである、即興音楽の出番です。
今井:即興で音楽をするというと、楽器ができない方にはハードルが高そうですが、大丈夫なのでしょうか?
長江先生:もちろん、大丈夫です。普段の会話と同じことをするだけですよ。皆さんも会話のときには形式的な受け答えだけではなく、相手によって返事やタイミングを変えて会話をしていますよね。
それをリズムや音程で行うイメージです。ジャズなどの即興とは異なり、対象者のニーズに合わせて、目的を持って即興的に音楽を行います。
そして対象者の表現する音や声、体の動きを音楽表現として捉え、それに合わせて、寄り添いながら、一緒に楽曲をつくり上げていきます。
このような音楽的なやり取りを通じて、自発的な表現やコミュニケーション能力を引き出していくのです。
そのため、ノードフ・ロビンズ音楽療法士には、より深い音楽療法の知識や、臨床即興として瞬時に応答できるような技術、さらには些細な音の変化を捉える敏感な耳が必要となり、認可を受けた機関でなければこのトレーニングは受けられません。
今井:対象になるのは、障がい児の方のみなのでしょうか?
長江先生:開始当時はそうでしたが、現在は幅広い方に向けて提供され始めています。
ノードフ・ロビンズ音楽療法の基本的概念の1つには、ミュージック・チャイルドというものがあり、これは誰しもが音楽を感じ、楽しむことができる力を持っているというような意味があります。
この力は、障がいや病気の有無にかかわらず、子どもから高齢者、終末期のケアを受けている方でも持っていることになります。
したがって対象とする年齢は幅広く、精神障がいをお持ちの方や脳梗塞後遺症による失語症の方、集中治療室に入院中の患者さんといった方々にも広がっています。
イギリスのノードフ・ロビンズ音楽療法センターさんのYoutubeチャンネルでは、実際の様子を見ることができるので、ご覧いただけると理解が深まると思います。
音楽は言葉を超えた非言語的コミュニケーション
今井:ここでの「チャイルド」は子ども向けという意味ではなく、誰もが音楽という母から生まれた子どもであるというニュアンスかもしれませんね。
私も拝見しましたが、ロック好きな子どもがプロのバンドマンの方と演奏している動画は、とても衝撃的でした。こういう形の音楽療法は、日本ではまだ少ない印象です。
今後、ノードフ・ロビンズ音楽療法が広まっていくことで、どんなメリットが増えていくのでしょうか?
長江先生:音楽は想像よりも身近なものであると認識してもらうことで、もっと音楽に触れる機会が増えてほしいと思います。
例えば、赤ちゃんとお母さんは、よく音を使ってコミュニケーションを取っています。
赤ちゃんが「んんま」「ダダー」と声を出したときに、お母さんが真似して返答したり、違う音を声で返したりすることは、非言語のコミュニケーションです。
会話ができる人同士が、「あ~」「ダ、ダ」などと言ってコミュニケーションを取るとしたら、少し変な感じがするかもしれませんね。しかし、誰でも一度は赤ちゃんだったのですから、実はどんな方でもできるはずです。
このように言葉を超えて創造的に参加し、関わり合いながら紡ぐコミュニケーションも、音楽となります。
さらに温かみのある、人とのつながりを感じる音楽は、心の健康を保つために大いに役立ってくれるでしょう。

音楽療法士は訓練されているので、これをとても音楽的だと捉えています。
コミュニケーションとしての音楽は音楽家だけができるものではなく、皆さんにもできるものです。そう考えたときに、音楽は楽曲という形だけではなく、とても身近なものだと感じられませんか?
そしてノードフ・ロビンズ音楽療法は、このような考え方を通して多くの音楽を提供していくことで、皆さんの豊かな日々を送るための手助けができると考えています。
在宅介護で活用する方法
今井:昔のTV番組で、司会者の方が足踏みでヒントを出すというのを思い出しました。
あれも音楽として考えたら、実はコミュニケーションとしての音楽はいろいろなところに隠れていて、それを気づかせてくれる存在なのかもしれません。
それでは最後に、ご家庭でも取り組める音楽の楽しみ方について教えてください。
長江先生:現在はスマホ1つでさまざまな音楽を手軽に楽しむことができますが、やはり肉声の良さという部分を活用してほしいです。
当たり前ですが、介護する方もされる方も人間なので、それぞれ日々体調や気分は変わります。さらに声は調子を表すバロメーターとして、お互い敏感に感じ取っています。
在宅介護をされている方は、ご家族を元気づけようとする一方、ストレスで強く当たってしまうこともあるのではないでしょうか。
もちろん人間なので仕方のないことですが、ここでより良い関係性を保つためのツールとして、音楽を活用してほしいと思います。
具体的には、さり気なく鼻歌を歌ってみることから始めてみてはいかがでしょうか?
今井:鼻歌でいいなら、準備するものも不要ですから、簡単に取り組めそうですね。でも、人前で歌うのはちょっと恥ずかしいと感じられる方も多いと思います。
長江先生:まずはテレビやラジオから流れてきた楽曲を口ずさんでみると、一緒に歌い始めたり、会話が始まったりするかもしれません。
テレビ番組やCMのBGMで使われている楽曲には、幅広い年代の方に親しまれているものも多くあります。
歌詞を覚えている方はそらで歌ってもいいですし、わからない部分は「ルルル~」とハミングでも大丈夫。声を出したり鼻唄をうたうことに慣れてきたら、次は気分でバリエーションをつくってみると良いですよ。
同じフレーズでも、明るく、切なく、怒ってなど、そのとき耳に残ったものから、取り組んでみてくださいね。
今井:その場で流れている楽曲に合わせるなら、ヒントもあるので簡単にできそうです。
鼻歌をキッカケに、お互いがより良い時間を過ごすためのコミュニケーションを増やしてほしいですね。
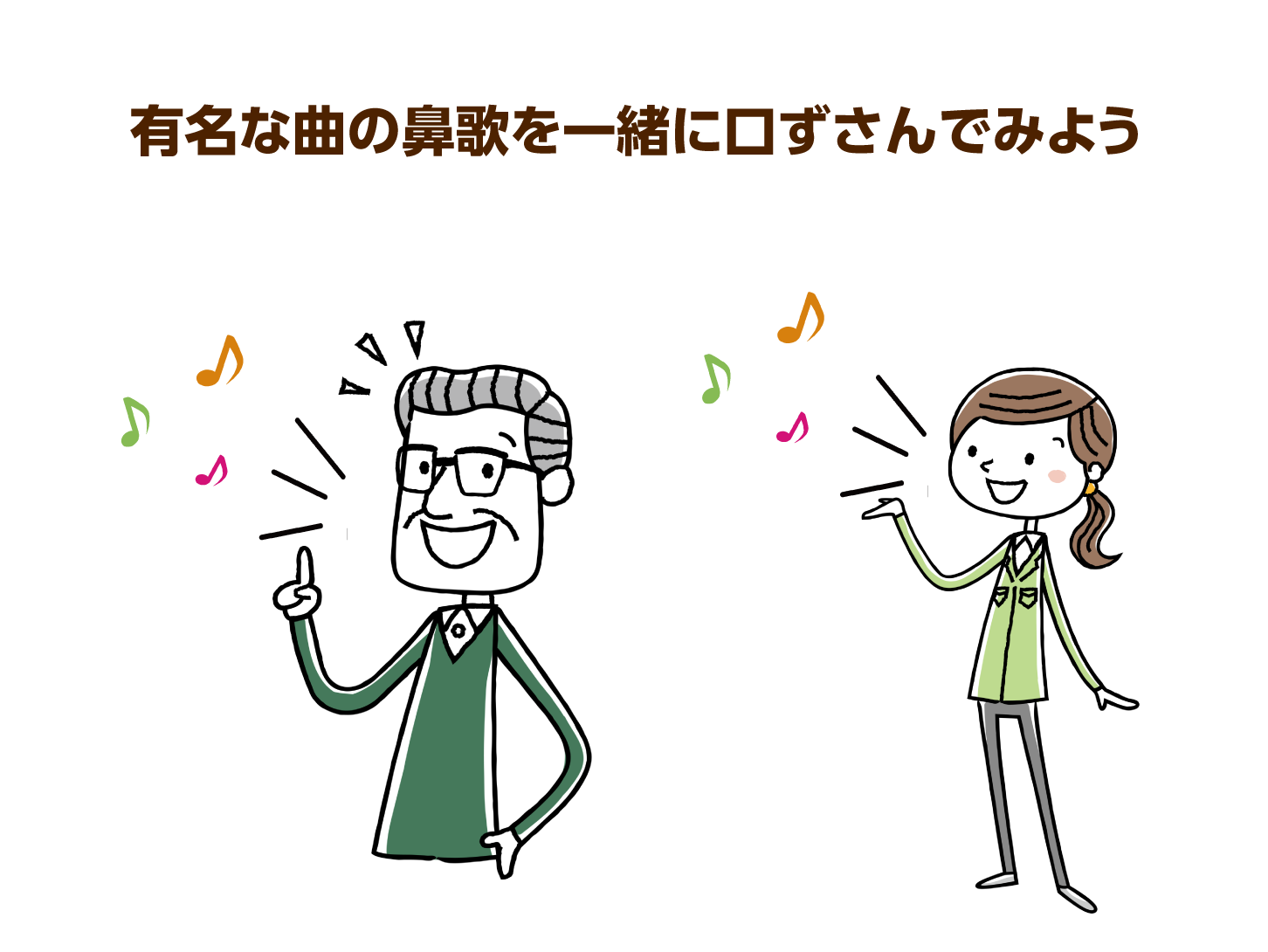
現在国内では、約15名のノードフ・ロビンズ音楽療法士さんが、さまざまな場所で活動されています。
さらに、長江先生が講師を務める名古屋音楽大学では、一昨年度よりノードフ・ロビンズ音楽療法士資格認定プログラムが開始され、2023年3月には認定を受けた先生方が複数名誕生する予定です。
今後もたくさんのノードフ・ロビンズ音楽療法士さんが活躍されていくことで、介護関係者はもちろん、たくさんの方の支えになっていくことを期待したいと思います。