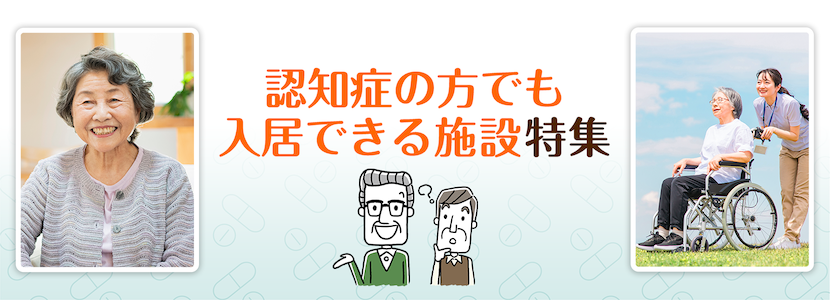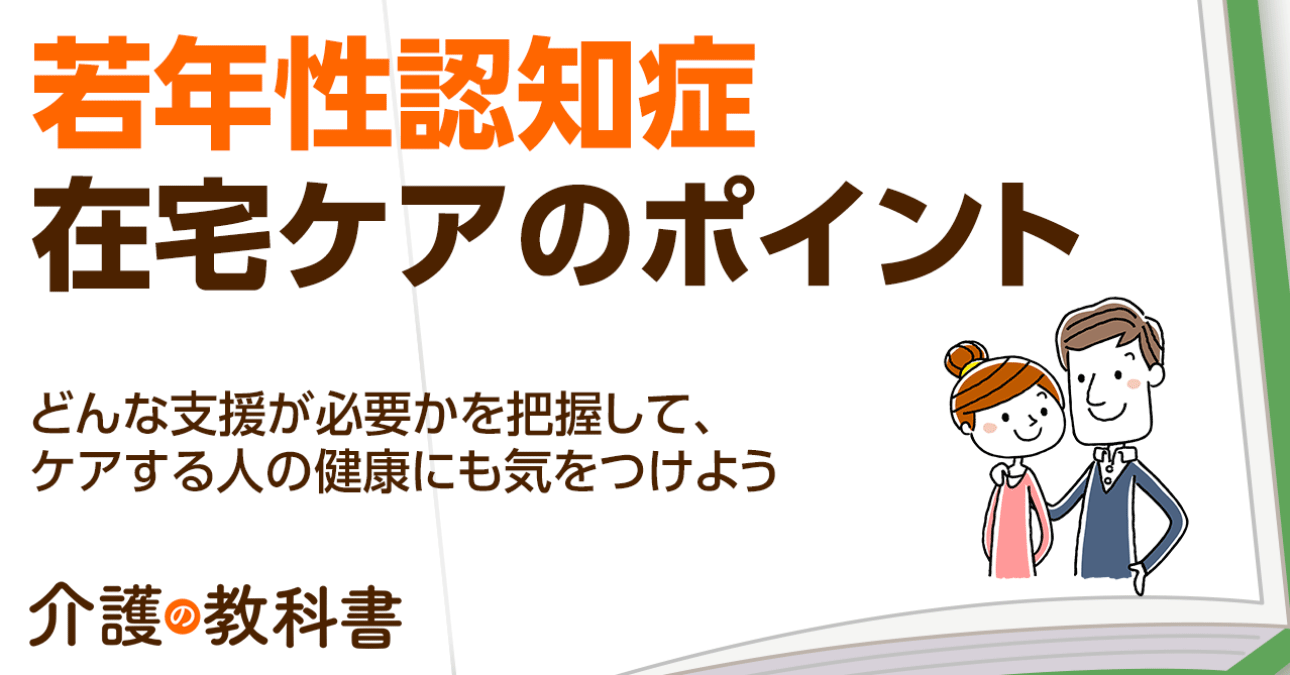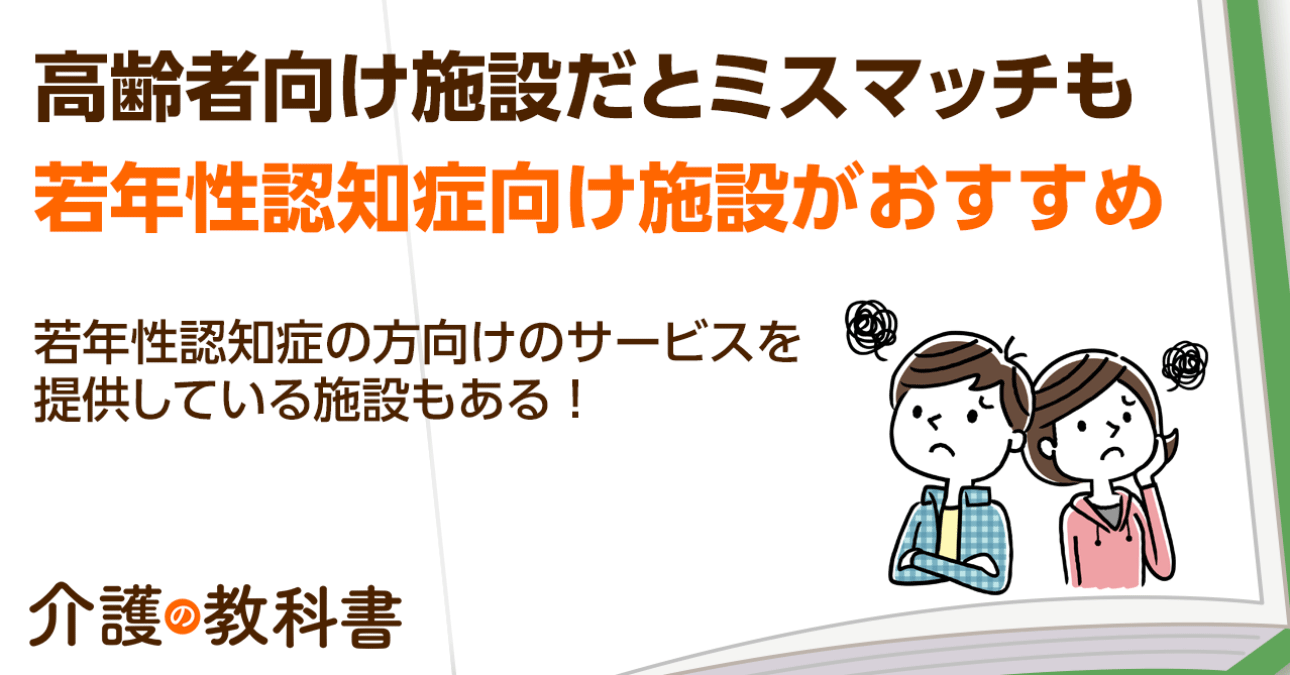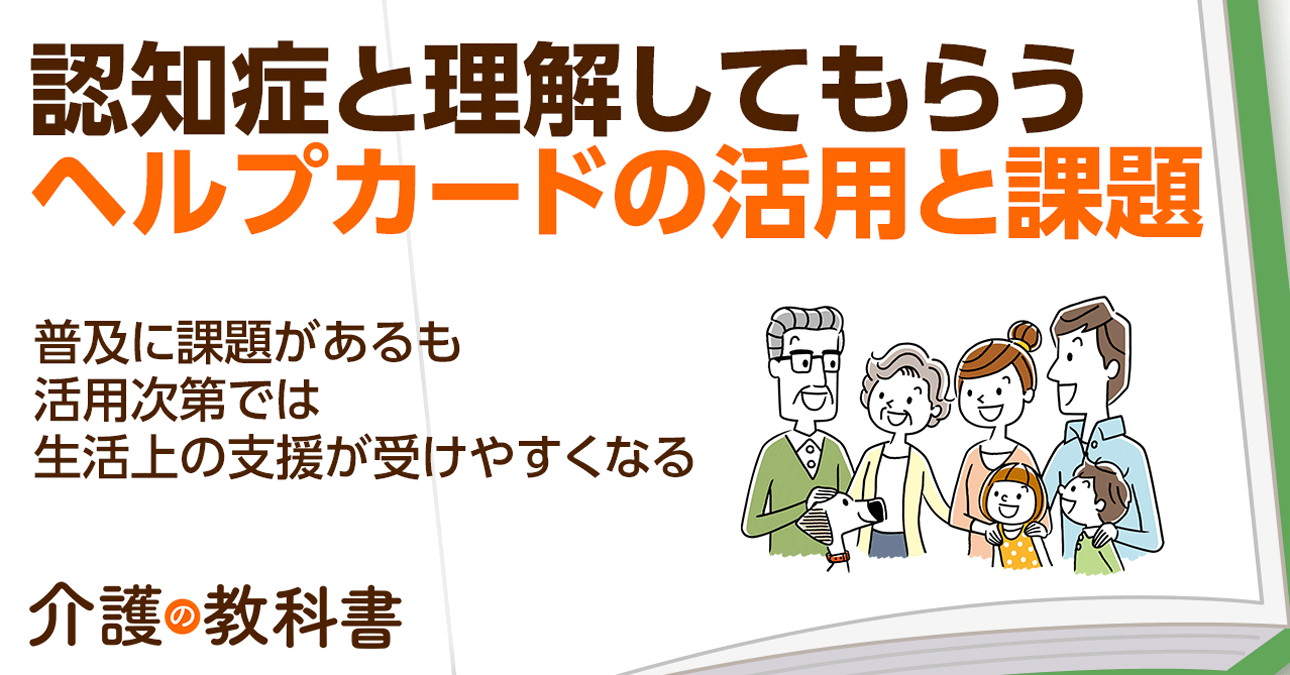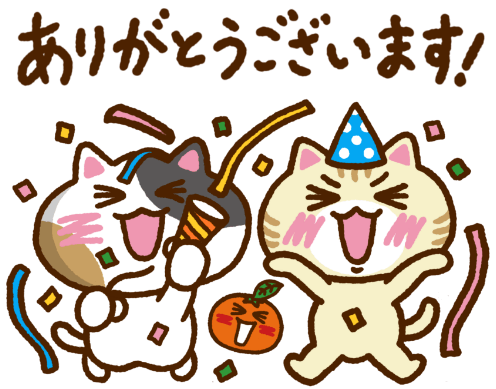若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症のことで、日本では約3万5千人が罹患していると推定されています。若年性認知症は、高齢者の認知症とは異なり、仕事や家庭に大きな影響を及ぼす可能性があります。しかし、若年性認知症に対する社会的な理解や支援はまだ十分ではありません。
今回、若年性認知症になっても働き続けたい人や、働けなくなった場合に再就職したい人に向けて、就労支援や雇用継続、再就職などの選択肢を紹介します。 若年性認知症について正しく理解し、自分に合った働き方を見つけるための参考にしてください。
若年性認知症について
若年性認知症とは、40歳から64歳に発症した初老期認知症に加えて、18歳から39歳までに発症した若年期認知症を加えた認知症の総称です。
若年性認知症という独立した病気があるわけでなく、発症年齢で区分した概念であるため、認知症を引き起こしている原因はさまざまで疾患も多様です。
若年性認知症を発症した場合、そのまま今の仕事を続けることができるかどうかは、その人の症状や能力、職種や職場の環境などによって異なります。
しかし、一般的には、認知機能の低下や行動障がいなどが進むと、仕事の質や量が低下したり、ミスやトラブルが増えたりする可能性があります。
そのため、早期に診断を受けて適切な治療を受けることはもちろんですが、就労に関しても自分の状況を把握し、必要な支援を受けることが重要です。
仕事を続けるうえで必要な就労支援には大きく分けて、雇用継続と再就職があります。雇用継続は、今の仕事をできるだけ長く続けることを目指します。一方、再就職は、現職を辞めて別の仕事に就くことを目指します。それぞれのパターンについて説明いたします。
雇用継続では、診断と周囲の理解がポイントになる
雇用継続に必要な支援は以下の通りです。
医師や専門家からの診断や治療
若年性認知症の発症のサインとしては、大事な取引先との打ち合わせや会議、書類の置き忘れなどがあります。また、家庭では家にあるものを忘れて何回も同じ買い物をしてしまうなどの症状が代表的です。
そのような症状が出てきたら「物忘れ外来」「脳神経内科」などの専門医を受診して、適切な治療を受けることが大切です。認知機能の低下を遅らせたり、行動障がいや精神症状を軽減させるなど、さまざまな治療効果が期待できます。
職場への理解や協力
現在の仕事を続けるためには、自分の症状や状況を職場に伝える必要があります。しかし、若年性認知症であることを明かすことは、本人や家族にとって大きな決断です。
若年性認知症に対する偏見や差別、解雇や降格などの不利益を恐れる気持ちもあるでしょう。そのため、誰に、いつ、どのように伝えるかは慎重に考える必要があります。
誰に伝えるかは、本人の信頼できる上司や同僚、人事担当者などが良いと考えられます。伝える時期は、症状が仕事に影響を及ぼす前に早めに伝えることが望ましいでしょう。
伝え方は、若年性認知症の診断書や医師の意見書などの客観的な資料を用意して、自分の症状や困りごとを具体的に伝えることが大切です。また、働き続けたいという意思や希望もしっかりと伝えましょう。
職場に伝えた後は、仕事の内容や量、難易度、ペースなどを調整してもらうことが必要です。例えば、以下のような方法があります。
- 職務内容の変更:自分の得意な仕事や興味のある仕事に変更する
- 職務範囲の縮小:仕事の量や難易度を減らす
- 職務手順の明確化:仕事の手順やルールをメモしたり、チェックリストをつくったりする
- 職務補助の提供:同僚や上司からのフォローやサポートを受ける
- 勤務時間の変更:勤務時間を減らしたり、柔軟なシフト制にしたりする
これらの方法は個人や職場によって異なりますが、本人と職場との間で話し合って決めることが大切です。また、定期的に評価や見直しを行うことも必要になります。
さらに、職場外でのサポートも利用することが有効です。例えば、以下のようなサポートがあります。
- 若年性認知症支援コーディネーター:若年性認知症の人が働きやすい職場づくりをサポートする役割を担い、すべての都道府県と一部の政令指定都市に配置されています
- 認知症カフェ:認知症の人やその家族、地域の人などが気軽に集まって交流や情報交換ができる場です。全国に約3,000ヵ所あります
以上が雇用継続のパターンについての解説です。雇用継続のパターンでは、仕事をできるだけ長く続けることを目指します。そのためには、医師や専門家からの診断や治療、職場への理解や協力、仕事内容や勤務時間などの調整、職場外でのサポートが必要です。これらの支援を受けることで、自分の能力や価値を発揮しながら働き続けることが可能です。
再就職の場合は円満な退職と再就職先の環境を考慮する
再就職をする際には、以下のような行動が必要です。
退職理由を伝える
退職理由が若年性認知症であることを伝えるかどうかは本人の判断次第ですが、できるだけ正直に伝えることが望ましいです。自分の症状や状況を受け入れることにもつながるし、職場からの理解や協力も得やすくなります。また、感謝の気持ちや今後の希望も伝えましょう。
退職後の生活費や保険などを確認する
退職すると収入が減るだけでなく、社会保険や雇用保険などの制度も変わります。そのため、退職後の生活費や保険などを事前に確認しておくことが必要です。また、退職金や年金などの受給に関する手続きも忘れずに行いましょう。
再就職先の探し方や選び方
再就職先を探す方法はいろいろありますが、以下のような方法が有効です。
- ハローワークや民間の人材紹介会社を利用する
- ハローワークや民間の人材紹介会社は、求人情報を提供するだけでなく、キャリアカウンセリングや履歴書作成などの就職支援も行っています。また、障害者雇用促進法に基づいて障がい者手帳を取得している場合は、障がい者専門のハローワークや人材紹介会社も利用できます。
- インターネットや新聞などで求人情報を探す
- インターネットや新聞などには多くの求人情報が掲載されています。自分の希望や条件に合った求人情報を探すことができます。ただし、インターネットや新聞だけでは情報が不十分な場合もあるので、応募する前に電話やメールで詳細を確認することが大切です。
- 知人や友人などから紹介してもらう
- 知っている人に紹介してもらうことで、信頼できる企業や仕事に出会える可能性が高まります。また、紹介者から仕事内容や職場環境などの情報を事前に得ることができます。
次に再就職先を選ぶ際のポイントを紹介いたします。
- 自分の能力や希望に合った仕事かどうか
- 自分の得意な仕事や興味のある仕事を選ぶことで、仕事へのモチベーションや満足度が高まります。また、自分の苦手な仕事や興味のない仕事を選ぶと、仕事の質や量が低下したり、ストレスが増え、若年性認知症に悪影響を及ぼす可能性もあります。
- 仕事の内容や条件が明確かどうか
- 自分の役割や責任を理解しやすくなります。また、仕事の内容や条件が明確になっていないと、期待と現実のギャップによって不満やトラブルが生じる可能性があります。
- 職場の環境や雰囲気が良いかどうか
- 職場環境は仕事への集中力に影響します。また、同僚や上司とのコミュニケーションや協力がスムーズになります。
再就職のためには、今の職場からの円満な退職、再就職先の探し方や選び方、再就職先での働き方が必要です。これらの支援を受けることで、自分に合った新しい仕事を見つけて働くことが可能になります。
まとめ
雇用継続と再就職のどちらのパターンも一長一短がありますが、自分の症状や能力、希望や条件などを考慮して決めることが大切です。
また、いずれにしても必要な支援を受けることで、働き続けることができます。働くことは生活を支えるだけでなく、自己実現や社会参加にもつながります。若年性認知症でも働きたいと思う人は多くいます。そのような人たちが働きやすい社会になるように、私たちも理解や支援を示していきましょう。