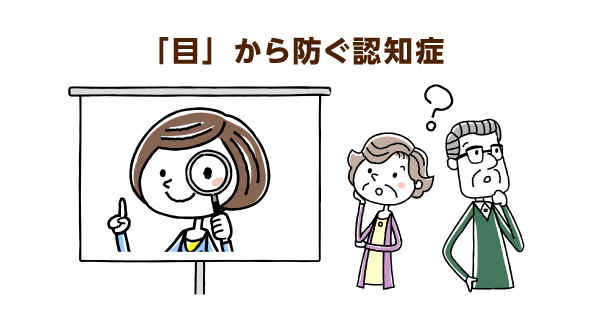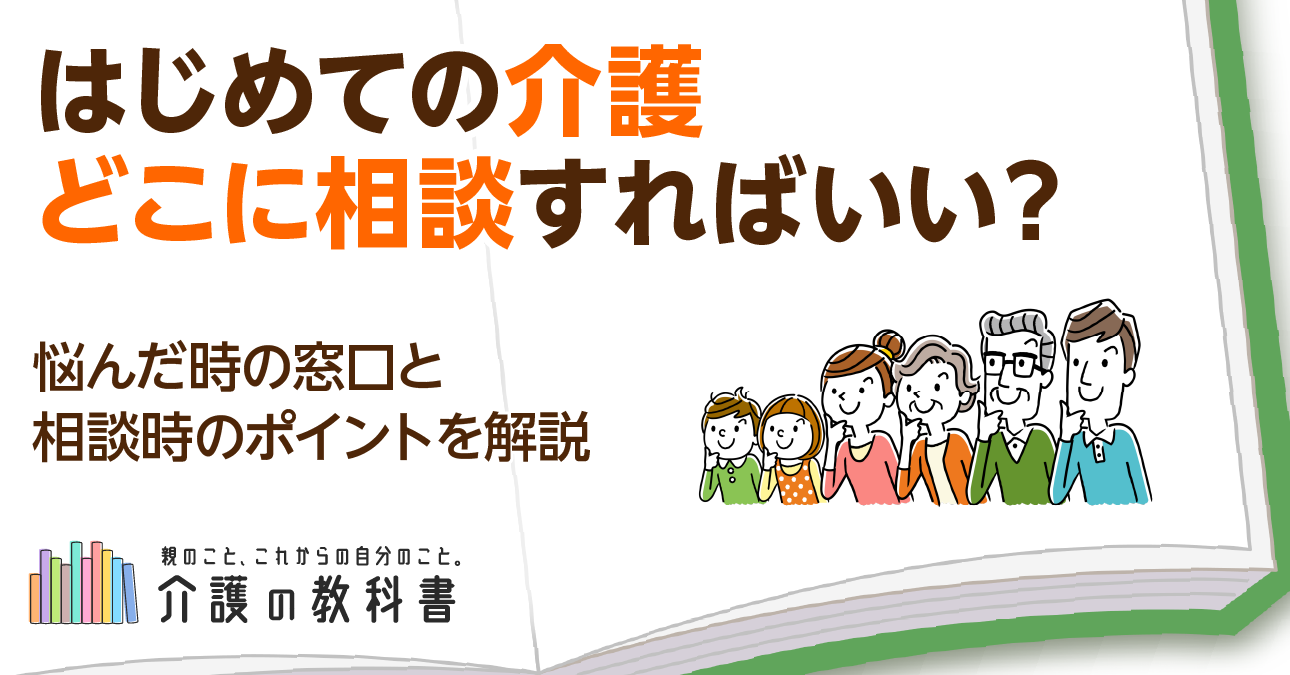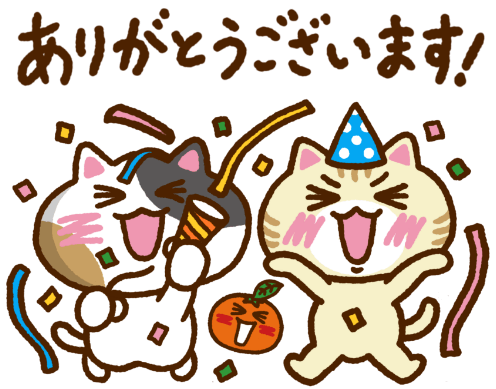皆さんこんにちは。医療と介護の連携支援センター長谷川昌之です。
今回は「地域ケア会議」について、事例を交えながら紹介していきたいと思います。
地域ケア会議の目的は住民のQOLの向上
皆さんは、「地域ケア会議」という単語を聞いたことはありますか?おそらく、ほとんどの方は聞いたことがなく、「何それ?」と思うのかもしれません。
地域ケア会議とは、地域における包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を効果的に実施するために、介護保険法第115条の規定に基づき設置される会議を指します。医療・介護関係の専門職のほか、福祉関係者、地域関係者や警察、消防関係者など、広範な関係者が集まって各関係者の知見を活かすとともに、各関係者の取り組みを進めることにより地域ケアにかかわるさまざまな課題の解決を図るのです。
地域ケア会議の目的は、地域包括ケアシステムの実現による地域住民の安心・安全とQOL(クオリティオブライフ)の向上です。機能としては下記の5つがあります。
- 個別課題解決機能
- ネットワーク構築機能
- 地域課題発見機能
- 地域づくり・資源開発機能
- 政策形成機能
これらは介護保険法に定められており、行政や支援センターに地域ケア会議の開催権限があります。地域ケア会議の構築と運営を繰りかえしていくことで、高齢者の方に対する支援の充実や社会基盤の整備につながります。また、尊厳のあるその人らしい生活を地域で継続することができる「まちづくり」(地域包括ケアの実現、増進)の形成につなげていくとのことです。
簡単に説明すると、「地域の困りごと(課題)は地域で解決しよう!」となるのでしょうか。

町田市が独自にガイドラインを作成
私の働く町田市を例に説明させていただきます。町田市における地域ケア会議については、『町田市地域ケア会議運営ガイドライン』(2020年4月作成)に従って進めています。このガイドラインが出された理由は、国が出す地域ケア会議の定義が漠然としたものであり、詳細は地域にゆだねられているものであったためです。地域(ここでは町田市を指します)はガイドライン発行以前から幾度となく開催していましたが、それが地域ケアにかかわるさまざまな課題の解決に至るのかは、非常に不透明な中で行われていたのです。
これまで行ってきた会議を活かすためにも町田市は、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築するために、個別ケースの検討(地域ケア個別会議)を始点として、個別課題の解決、地域ネットワークの構築、地域課題発見、地域資源の開発を遂行。さらには全域的な政策形成までを行う地域ケア会議(地域ケア推進会議)が効果的に開催することが求められています。
これらの背景を受けて、町田市では「地域ケア会議」の全体像および運営方法について示すとともに、市と高齢者支援センターや医療、介護の連携支援センターが果たすべき役割について明確化しました。
町田市が定める定例会議
- 地域ケア会議…個別ケースの検討を行う
- 地域ケア推進会議…地域の新たな資源開発や施策立案を提言する
「地域ケア個別会議」については、ケアマネージャーが行う「サービス担当者会議」と混同されますが、「サービス担当者会議」は、介護支援専門員の主催により、ケアマネジメントの一環として開催するものです。効果的で実現可能である居宅サービス計画とするため、利用者の状況などに関する情報を各サービス担当者などと共有するとともに、専門的な見地から意見を求めて、具体的サービスの内容の検討や調整を図るものです。位置づけは地域ケア会議とは異なっています。
住民や支援関係者の役割を整理して地域ケア会議を実施
ここまで地域ケア会議についての法律上の説明と町田市におけるガイドラインなどを説明させていただきましたが、まだイメージがつきにくいと思いますので、1つの事例を紹介させていただきます。
Aさん(ケアマネージャー)から高齢者支援センター(町田市における地域包括支援センターのこと)に、以下の内容で相談がありました。
Bさん、90歳男性、要介護1
- 最近混乱が多く理解力が低下している状況
- 腰痛もあり外出の機会も減少
- 今までかかわりを持っていた主治医の訪問診療・介護保険サービスを拒否
- 食材について、同じものを購入したり腐らせたりする状況が見受けれる
- 金銭管理を行えているか不安であり、担当者会議の開催を提案してもBさんから拒否
その相談を受けて高齢者支援センターは、Bさん宅を訪問し状況を確認。併せて担当の民生委員さんや親族にも、状況確認と情報収集を行いました。
その過程で、遠縁の姪から医療機関への受診拒否をしていることに対して支援者が非常に困っていること、民生委員からは以前に比べて訪問しても拒否されたり、お話されることも少なく心配だったことがわかりました。
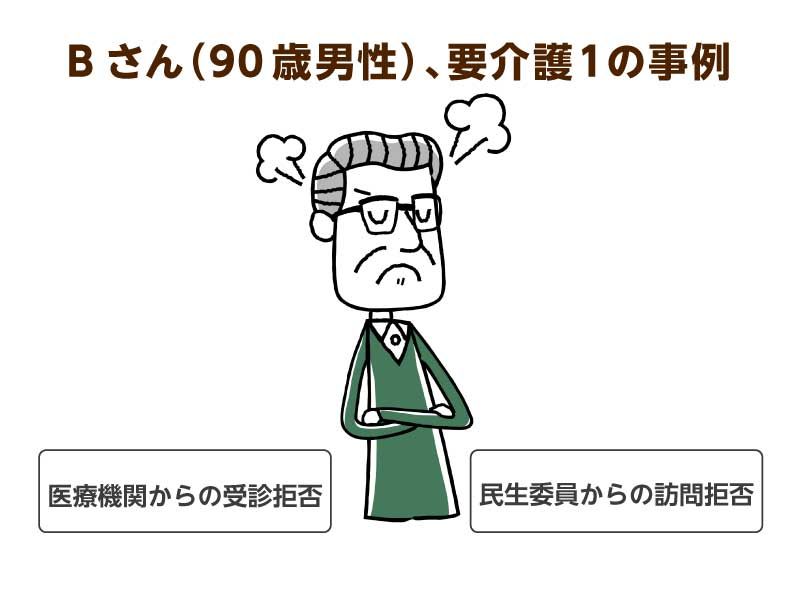
その情報から、4つの状況が想定されました。
- B氏のサービス担当者会議の開催拒否・地域ケア個別会議への参加がB氏のサービスにおける理解促進の機会になると考え、地域ケア個別会議によるB氏の支援内容の検討が適切だと想定
- Aさんの、自立支援に資するケアマネジメントの実践力を向上できる
- 医師や民生委員など、地域に影響力のある方の参加が地域包括支援ネットワークの充実化につながる
- Bさんの居住地域は独居や高齢者世帯の割合が高いので地域の困りごとを把握できる
上記の想定を踏まえ、地域ケア個別会議の開催を決定しBさんへ提案しました。この結果、地域ケア個別会議開催と参加の了解を取り付けることができたのです。
この想定される課題解決のために、地域ケア個別会議へ誰に参加いただくのがベストか、ケアマネージャーと高齢者支援センターで協議を行い、以下の人物が当てはまりました。
各場面で重要な人物
- Bさんが地域での望む生活の継続
- 主治医や民生委員、社会福祉協議会
- ケアマネの実践力向上
- 高齢者支援センターの主任ケアマネや事業所の管理者
- 地域包括支援ネットワーク構築
- 民生委員、近隣のスーパーの方
- 地域課題を把握し今後の検討
- 地域の多様な方
参加者をしっかりと決めてから、地域ケア会議を行っていくことになります。ここで大切なのは「Bさんの望む生活とは何か?」についてしっかり確認し、決して地域から除外するのではなく、Bさん自身も「地域の一員」と思っていただくことです。
地域ケア個別会議による4つの成果
地域ケア個別会議の成果(目的)としては、下記が果たされたと考えます。
- Bさんの理解が深まり、訪問診療を再開、訪問介護などの介護保険サービスが決定
- ケアマネA氏の実践力が高まり、介護保険外のサービスもプランに組み込み
- 医療機関側とケアマネ・介護関係者との連携に関する取組への協力を獲得
- Bさんの居住地域は独居や高齢者世帯の割合が高いので地域の悩みを把握可能
この地域ケア個別会議を経て、Bさんについては一応の解決が図られました。ただこの1つの事例から地域での同じような案件はないのか、もしほかにも案件があるのであれば、地域として解決していく課題になるので、地域ケア推進会議に図る形になっていきます。
今回はケアマネージャーが支援困難になったケースを想定しましたが、認知症の方の問題や難病の方など問題・課題は多岐にわたります。個人の問題が地域での解決すべき課題と認識され、最終的には市全域としての問題・課題となり解決方法を検討していくことになります。
地域包括支援センターでも認知度は約5割、住民への周知が必要
以上、なるべく簡単にわかりやすい形でお伝えしたつもりではありますが、一般の方だと本当に「馴染み」のない部分です。ぜひ専門職の方には知っていただいて、地域包括支援センターとうまく活用していただきたいと思っています。上記事例などは、各市町村において運用の仕方など違いがあるので町田市での運用とご承知おきください。
町田市のデータにはなりますが、包括支援センター(町田市では高齢者支援センター)がいかに周知されているか市民に周知度アンケートを取りました。地域包括支援センターを知っており、かつ場所がわかる方は約50%という結果になりました。まだまだ包括支援センターやその役割については周知不足の点はあり、その中でもこの「地域ケア会議」の活用についてはさらに周知が必要なのかもしれません。