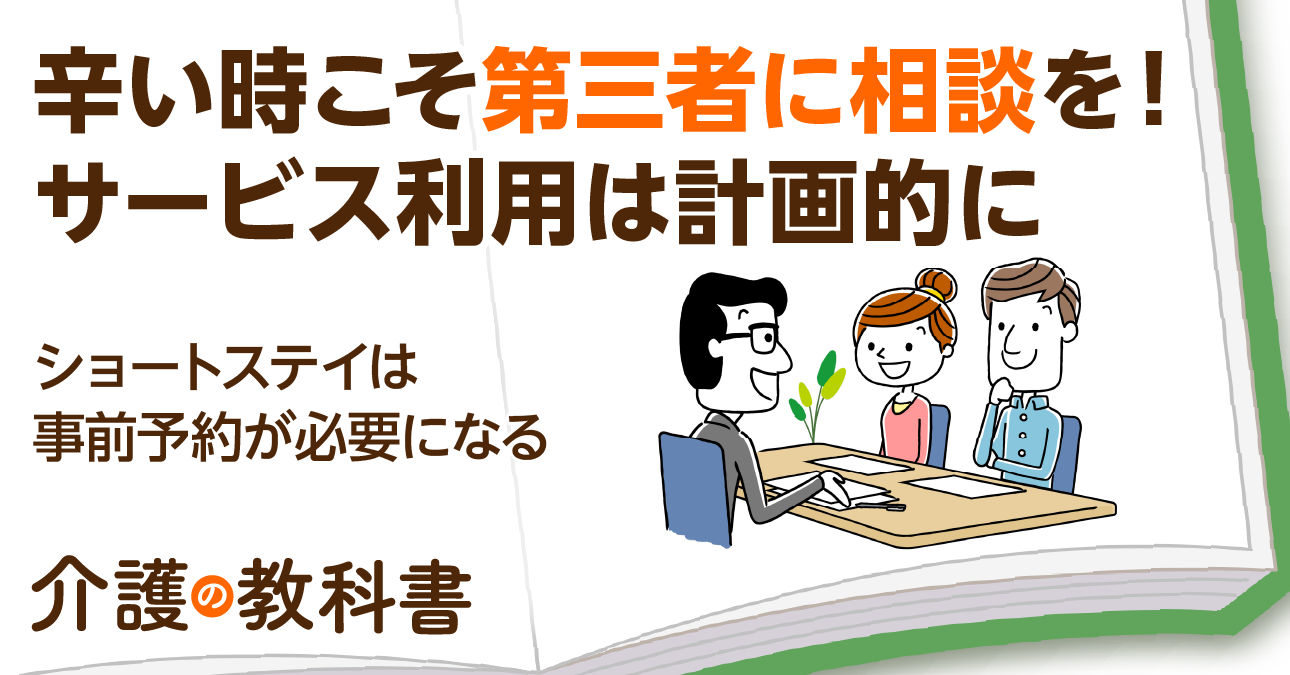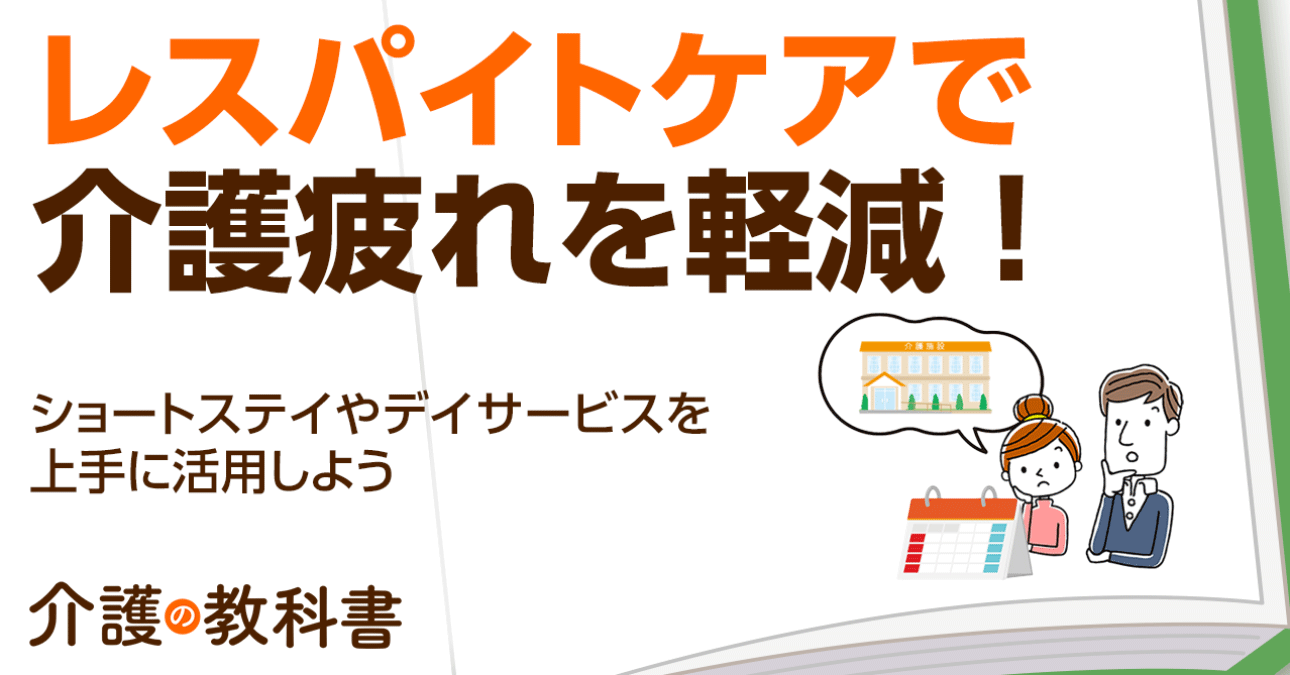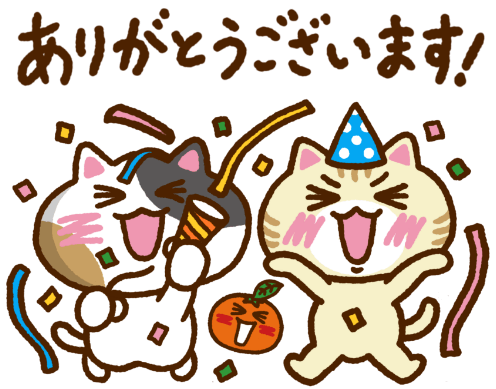介護保険サービスのショートステイを利用したことはあるでしょうか。
2024年4月の介護保険報酬改定に向け、厚労省の社会保障審議会・介護給付費分科会で、ショートステイの長期利用(ロングショート)について議論が行われました。
厚労省は、現状のショートステイでは、長期利用をすると施設入所と同等の利用実態になっていることを指摘。そこで長期利用時の報酬と特養入所時の報酬を均衡させるて適正化を図ることを提案しました。本来の目的に応じた利用を促していく観点から、具体的な検討を進める意向です。
この改定によって、利用者にどのような影響があるのか解説していきたいと思います。
ショートステイの制度と料金

まずはショートステイについて簡単に説明しましょう。
介護保険制度におけるショートステイは、短期入所生活介護・短期入所療養介護と呼ばれています。現状では、利用者ができる限り在宅で生活を歩めるよう老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所できるサービスになっています。
具体的なサービス内容には、入浴、排泄、食事などの介護に加え、機能訓練などがあります。
本来、ショートステイは短期間の入所を目的としており、連続して1日~30日の利用を想定しています。主に生活介護と療養介護で以下のような料金区分が設けられています。
| 従来型個室・多床室 | ユニット型個室 | 従来型個室・多床室 | ユニット型個室 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 約600円 | 約700円 | 約630円 | 約740円 |
| 要介護2 | 約670円 | 約770円 | 約710円 | 約810円 |
| 要介護3 | 約740円 | 約840円 | 約780円 | 約880円 |
| 要介護4 | 約810円 | 約910円 | 約850円 | 約950円 |
| 要介護5 | 約870円 | 約980円 | 約920円 | 約1020円 |
| 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 約750円 | 約830円 | 約830円 |
| 要介護2 | 約800円 | 約880円 | 約880円 |
| 要介護3 | 約860円 | 約940円 | 約940円 |
| 要介護4 | 約910円 | 約990円 | 約1000円 |
| 要介護5 | 約970円 | 約1050円 | 約1050円 |
上記の金額に加え、介護や看護体制などの加算や食費などの実費が加わるため、施設によって料金はちがいます。
ロングショートを利用する人の事情
「短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握に係る調査研究事業」報告書によると、最も利用日数で多かったのは2~3日の利用で全体の約4割。次いで4~7日で全体の約3割を占めています。31日以上利用するロングショートは1割未満です。それにもかかわらず、なぜ問題視されているのでしょうか。
そもそも介護保険でのショートステイでは30日を超えて長期に利用する場合について、以下の規定を事業所に課しています。
- 30日を超える日以降に受けたサービスについて、短期入所生活介護費を算定することができない
- 自費でのサービス利用を挟み、同一事業所を連続30日利用している方に対してサービス提供をする場合は、連続30日を超えた日から減算を行う
簡単にいってしまえば、減算対象として認めてはいるものの適正な利用ではないという意味が込められています。
一方、ロングショートを利用する理由として「特養入所までの待機場所として」が最多となっています。その理由はどこにあるのでしょうか。
一つに、ショートステイが設置されている場所があげられます。厚労省の調査によると、ショートステイは全体の約8割が老人短期入所施設、特別養護老人ホームなどに併設されています。
ショートステイの本来の目的は、自宅での生活が困難になった方や、介護者の負担軽減を図ることを目的としています。
しかし、実際には自宅での生活がさまざまな理由で困難となり自宅に戻れない方が、そのまま特養に入居するまでショートステイを利用するというケースがあります。
私が聞いたところによると、次のような方がロングショートをしていました。
- 一人暮らしだったり、家族に要介護者や障がいのある方がいる状況で、本人の要介護度が重いとき
- 片付けられなかったり、家屋の状況が悪化するなど、衛生状況が悪い方
- 虐待されていて、同居が困難
- 特養に入居認定をされているもののそれまで住む場所がない
- 経済状況が悪く、有料の施設入居が難しい
このような状況の方が、しかたなく利用している状況があります。つまり、特養などに入居待ちをしている前提で利用されているので、施設への入所と同等の利用形態になっているのです。
緊急性の高い事案の一時避難としても活用される
サービスの適正利用は望ましいことだと思いますが、前述のようなケースは、利用者自身が望んでいたわけではなく、しょうがなく長期利用をしなければならない状況に置かれています。
例えば、虐待を受けて特養などに入居が必要となった場合について考えてみましょう。
虐待のケースでは保護の緊急性が高いものの、介護度の重い方は行き先が限定されます。何らかの治療が必要であれば、病院などの医療機関も考えられますが、治療の必要がなければ入院はできません。その場合は、避難先として老人短期入所施設、特別養護老人ホームなどが選ばれます。
特養に入所する入口として、ショートステイの利用から始めるという方法は合理的です。一方で、虐待の問題が解決しない限り、自宅には帰れないため、結果としてロングショートを利用してしまうこともあるでしょう。このようにショートステイが緊急時の受入れ先として活用されることがあるのです。
メリットとデメリットを考慮して適正利用につなげる

ショートステイの利用は、在宅生活を支えていくためには非常に有用です。なかでも、ロングショートは個別の事情に配慮し、利用者の安心・安全を確保するという点でメリットが大きいと考えられます。
一方で、医療機関での受診を制限されるというデメリットもあります。
本来ショートステイ利用中は基本的に施設に配置された医師による診察を受けることになっています。しかし、実態としてショートステイは在宅扱いになるため、ほかの医療機関での受診を求められるケースが多く発生しています。
その場合、受診の同行を誰が行うのかといった課題が発生します。入居していれば施設のケアマネが担当しますが、在宅扱いの場合は居宅ケアマネが担当することになります。
ロングショートは正式な入居者と変わらない状況にありながら、入居者と同様のサービスを受けることが困難です。
ショートステイの適正な利用については、問題や課題が比較的はっきりしています。今回の改定で一律に制限を設けて、本来支援を受けれる方が受けられない状況に陥ることは避けなければなりません。個別の実態に合わせて検討する必要があります。まずは、代わりとなる施設や受け皿になりうる制度をしっかりと整えることが必要ではないでしょうか。