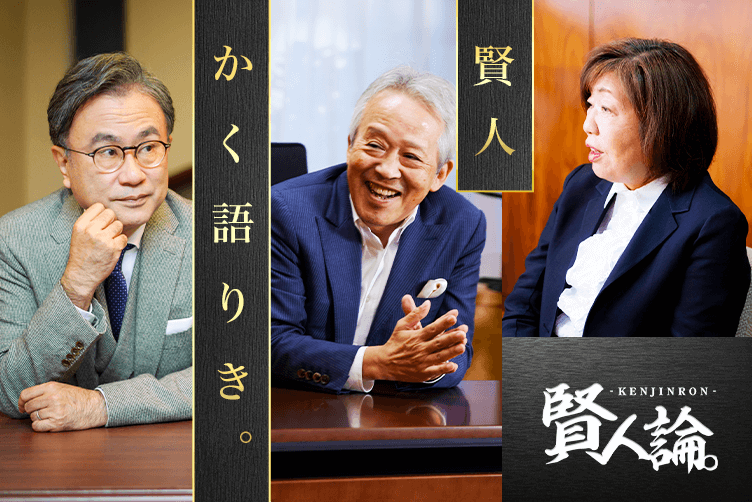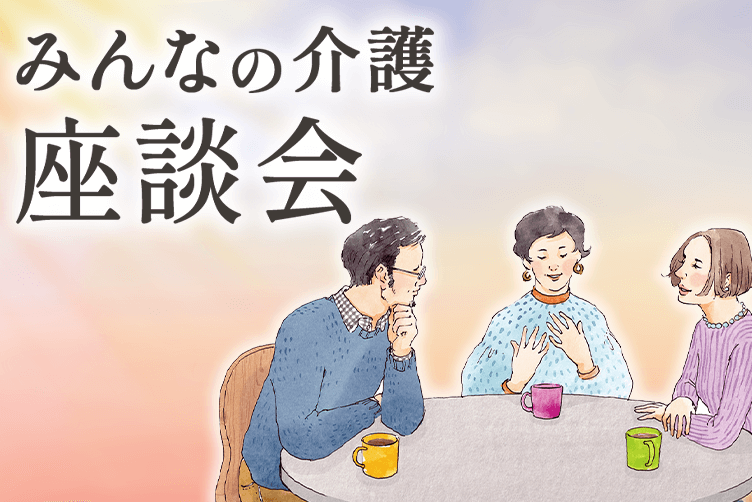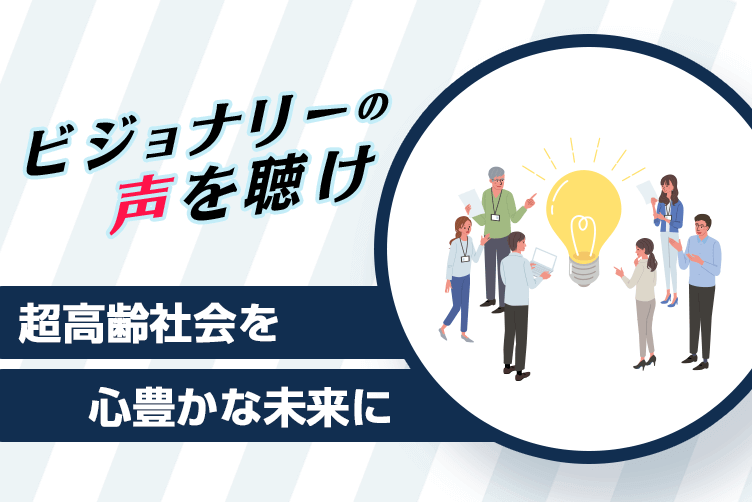みんなの介護ニュース コンテンツポリシー

『みんなの介護ニュース』とは
老人ホーム検索サイト「みんなの介護」が運営するオウンドメディアです
いま介護をしている方、今日も現場で働く方、これから介護に直面するかもしれない方、社会保障に関心のある方、全ての人に役に立つ情報を提供すべく、2011年に『みんなの介護ニュース』は生まれました。
各界識者へのインタビュー「賢人論。」、専門家がわかりやすく伝える「介護の教科書」、官公庁のデータから超高齢社会を読み解く「ニッポンの介護学」など、連載を中心に毎日最低1本、コンスタントにコンテンツを配信しています。
編集チームの想い

2021年の人口統計で、日本の総人口に占める65歳以上高齢者の割合は29.1パーセントに達しました。世界に先駆けて超高齢社会となった日本で、介護はこれから国民全員が“ジブンゴト”として直面し、向き合わなければならない問題です。
この大きな社会課題に対して、私たちがつくるコンテンツで一人ひとりの選択肢を増やしていきたい。私たちが起点となって社会を前向きにエンパワーメントしていきたい。編集チームはそんな想いを持っています。
6つの編集指針

1 “心を動かすのか”を問い続けます
編集チームでは良いコンテンツの条件を「心を動かすもの」と言語化しています。 本質的な情報とは、納得・驚き・楽しさといった感情を読者の記憶に残し、その後の行動や人生を変えるものであると考えます。 「このコンテンツは心を動かすだろうか?」私たちは常に問い続けます。
2 “多種多様な価値観”を尊重します
寄稿記事やインタビューにおいて、書き手や識者の価値観を最大限に尊重します。 トピックが革新的であればあるほど、普遍的な価値観で測ることは難しくなります。編集者は、まず第一の読者として思い込みを捨て、フラットに受け止める事に努めます。 年齢や性別、思想や信条などの違いを認め、「ダイバーシティ&インクルージョン」で多種多様な価値観を拡張します。
3 “事実や根拠”を明確にします
一方で、定性的なあいまいさは極力排していきます。事実ベースのコンテンツづくりをするべく、各省庁の一次情報に必ず当たり事実を確認します。 また、出典元を明らかにした上で、公的データや論文を積極的に引用し、主張を裏付ける根拠を補足します。そして、当該テーマの専門家に内容の正確性について監修を依頼し、専門性を担保します。
4 “さまざまな表現手法”に挑戦します
一つひとつコンテンツの特性を見定め、どういった見せ方であれば読者に直観的に届けられるか。読者ファーストに立って考え抜きます。 その手段としてテキスト記事だけでなく、動画や漫画などさまざまな表現手法に挑戦。中身だけでなく見せ方にもこだわって、今後もその幅を広げていきます。
5 “一人ひとりの声”と真摯に向き合います
介護の当事者は、いま何に悩み、怒り、喜びを感じているのか。そして、私たちが制作するコンテンツに対してどのような意見をお持ちなのか。読者一人ひとりの声に耳をすませ、向き合い、お応えしていきます。 コメント欄など記事へのリアクションの場を設け、ユーザー同士が直接情報交換出来るコミュニティもサービスとして提供します。
6 “ちょっと先の未来”を届けます
変化の速い現代において、社会の姿は日々刻々と変わっています。視点が“いま”ではあっという間に情報は陳腐化します。かと言ってそれが遠すぎても絵空事になって、読者の実生活に有益なものとはなりません。 私たちは“ちょっと先の未来”に回って、介護や社会保障のあり方、ライフスタイルについて、新しい視点を提供したいと考えています。
コンテンツ制作フロー(※ニッポンの介護学の例)

STEP 1
読者のニーズを満たすテーマであるか、主張を支える事実・根拠があるか、『みんなの介護ニュース』ならではの独自の視点や切り口が提供できそうか。編集チームで議論を交わし記事のテーマを決定します。
STEP 2
各省庁発表の一次情報、統計データをベースに独自取材も重ね、原稿を制作します。
STEP 3
誤字脱字がないか、図らずも他の記事と似た内容になっていないか。校正ツールと、編集デスクによるダブルチェックを行います。
STEP 4
記事公開前に外部の専門家に監修を依頼し、正確な内容であるかファクトチェックを受けます。
STEP 5
上記のフローを経て、テーマ会議から1ヵ月程度時間をかけ1つの記事を公開します。
STEP 6
「公開したら終わり」ではなく、公開後に必ず編集チームでレビューをします。訂正すべき点が見つかれば、修正日を明記して内容をアップデートします。
田代 真執行役員 兼 チーフコンテンツオフィサー
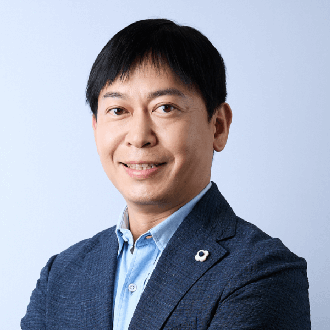
早稲田大学を卒業後、大手出版社に新卒入社。編集と営業業務に従事した後、創業して間もない楽天株式会社に入社しコンサルティング営業に従事。2007年日本オフィスを立ち上げたばかりのGoogleに入社。
Googleにて約16年間大手クライアントを中心に、リスティング広告やYouTube広告などの普及に従事し、2022年にクーリエ参画。現在は執行役員兼CCO(チーフコンテンツオフィサー)としてオンラインとオフラインを統合したマーケティングとコンテンツ戦略を牽引。
監修者紹介
新井平伊順天堂大学医学部名誉教授
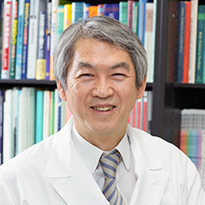
順天堂大学医学部名誉教授、アルツクリニック東京院長。「アルツハイマー病研究者 世界トップ100」にも選出された研究者であり、認知症に対して国内屈指の知見を持つ。主な著作に『脳寿命を延ばす 認知症にならない18の方法』(文藝春秋)など。みんなの介護でも「認知症」に関する記事を多数監修している。
武久洋三(一社)日本慢性期医療協会名誉会長

(一社)日本慢性期医療協会名誉会長。「日本一の慢性期病院を目指す」という理念のもと1984年に博愛記念病院を開業。一人でも多くの患者が日常生活に復帰できるようリハビリの重要性を長年発信してきた。主な著作に『令和時代の医療・介護を考える』(中央公論事業出版)など。みんなの介護では「病気」や「終末医療」に関する記事を多数監修している。
柴口里則(一社)日本介護支援専門員協会会長

(一社)日本介護支援専門員協会会長。協会会長として、ケアマネージャーの質や社会的地位の向上を目的に、介護報酬や給与水準の引き上げに注力している。また「ケアプラン作成支援AIの実証実験」にも貢献。介護保険制度や補助金制度などに精通しており、みんなの介護の「介護制度」や「業界が抱える課題 」に関する記事を監修している。
小濱道博小濱介護経営事務所代表

介護事業コンサルタント。『小濱介護経営事務所』代表。会計事務所に17年間勤務した後、『小濱介護経営事務所』を設立。介護経営のコンプライアンス指導のほか、自治体や社会福祉協議会の講習会などの講師や書籍の執筆活動も行っている。主な著作に『これならわかる〈スッキリ図解〉介護BCP』(翔泳社)がある。みんなの介護では、連載「カイゴのおカネクラブ」の監修に協力。
天野清一都心綜合会計事務所代表

税理士。税理士法人『都心綜合会計事務所』代表、全国相続協会相続支援センター室長。1977年の税理士事務所開業以来、数多くの相続案件を担当。著作に『中小企業再生の実務』(日本評論社)がある。みんなの介護では、税理士ならではの視点から「相続」や「老後にかかる費用」に関する記事を監修している。
著作権・利用について
コンテンツの著作権は株式会社クーリエ(以下「当社」と言います)に帰属します。法律により認められた範囲内での引用を除き、無断でのダウンロード、コピー、配信、掲示、送信、削除、変更、翻案等の利用は固くお断りします。
テレビ放送や新聞・雑誌、広告などにコンテンツを使用される場合は、まずお問い合わせください。
【お問合せ】editorial@courier.jpn.com免責事項
上記編集方針、コンテンツ制作フローに基づきコンテンツを制作し細心の注意で運営・管理をしておりますが、お客様が当社ウェブサイトを利用されたことによって生じるいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。